楽園への道
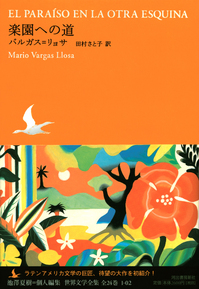 バルガス=リョサの2003年の作品が「河出世界文学全集」の第二巻として刊行された。この文学全集、初訳が少ないのだが、この巻は初訳で、全集の目玉の一つと言えるのではないだろうか。フローラ・トリスタンとポール・ゴーギャン。違う時代に生きた祖母と孫だが、共通点は波乱に満ちた生涯を送ったこと、そしてペルーである。フローラの父親はペルー人で、成人後ペルーを訪れ、得難い体験をしており、この女性が労働運動家・女性運動家として活動するきっかけを作ったのは、ペルーの女性たちの自由さだったという。また、ゴーギャンも幼い頃ペルーで過ごしている。特にゴーギャンの南方指向にはペルーでの幼児体験が大きく影響しているとリョサは考えている。
バルガス=リョサの2003年の作品が「河出世界文学全集」の第二巻として刊行された。この文学全集、初訳が少ないのだが、この巻は初訳で、全集の目玉の一つと言えるのではないだろうか。フローラ・トリスタンとポール・ゴーギャン。違う時代に生きた祖母と孫だが、共通点は波乱に満ちた生涯を送ったこと、そしてペルーである。フローラの父親はペルー人で、成人後ペルーを訪れ、得難い体験をしており、この女性が労働運動家・女性運動家として活動するきっかけを作ったのは、ペルーの女性たちの自由さだったという。また、ゴーギャンも幼い頃ペルーで過ごしている。特にゴーギャンの南方指向にはペルーでの幼児体験が大きく影響しているとリョサは考えている。
ゴーギャンの方は1892年4月に最初にタヒチに着いた時から物語は始まる。同年「死霊は見ている」はテハッアマナというタヒチに渡って2番目の愛人がモデルである。
床に敷いた敷布団の上で、裸でうつ伏せになったテハッアマナが、丸みを帯びた尻を少し浮かせ、背中をやや曲げて、顔を半分彼のほうに向けながら、動物のようにひどくおびえた表情で、目も口も鼻も引きつらせたまま顔をしかめるようにして、彼を見つめていた。
「マナオ・トゥパパウ」と名付けられたその絵は、ゴーギャンがヨーロッパではもう見つけることの出来ない何かに触れた、幻想的な経験だった。
1893年「神秘の水」(パペ・モエ)は中性的な少年を描いた、水彩画である。
花や葉、水、淫らな形をした石の森の真ん中で、岩にもたれ、渇きをいやすためか、その土地の見えない神をあがめるためか、その陰影のある美しい身体を小さな滝のほうに傾けている一人の人間である。
「アイタ・タマリ(ジャワ女アンナ)はゴーギャンがパリに戻った後、一緒に暮らした女性だが、その絵の裏には実はジュディットというモラール家の令嬢が描かれているというリョサの解釈が書かれている。
ゴーギャンが再び タヒチを訪れ、描いた「ネヴァーモア」はゴーギャンの子を妊娠中のパウッウラを描いたもので、失敗に終わった自殺を前に描いた大作「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」の詳細な解説もある。最晩年の「ヒヴァ・オアの呪術師」(妖術使いあるいはヒヴァ=オア島の魔法使い) の男とも女ともわからないように呪術師を描いている。このモデルになった人物も登場する。
というように、まずはゴーギャンの画集を購入した方が良いと思う。リョサ自身もゴーギャンの絵の入ったものを刊行することが希望だそうだが、それも当然だろう。
フローラ・トリスタンを知っている人はプロレタリア思想などに詳しい人だけではないだろうか。ジョルジュ・サンドは知っていても、フローラ・トリスタンは知らないのは仕方あるまい。リョサがこの人を発掘してくれなかったくれなかったら、私はずっと知らないままだったのではないだろうか。彼女の著書「ペルー旅行記―ある女バリアの遍歴」「ロンドン散策」は邦訳が出ている。
パリは世界でも最も女性の強い街だろうと思うが、こういう人たちが150年以上前にえらくひどい目に遭って、戦って勝ち得て来たものなのだろう。
ゴーギャンとトリスタンの二人の物語が交互に進行するが、互いに浸食し合うことはない。彼らの生涯のうち最晩年の頃が時系列に物語られつつ、彼ら自身が回想する形で遡って伝記がたどられる。騎士道物語の体裁をとっているそうで、突然語り手が主人公たちに語りかけるような調子が入るが、基本的に第三者の語り手のまま、混乱することなく進んでいく。
リョサの初期の作品に比べれば、小説技法としては拍子抜けするほどわかりやすく、画期的な試みは見られない。ゴーギャンとフローラ・トリスタンの手紙や著作などの歴史的事実をベースに著者が自由にフィクションを作り上げていることは見て取れる。だが、やもすれば普通の歴史小説のようで、少々物足りなさを感じてしまうのは私だけだろうか。量的には500ページ以上なので、充分すぎるほど充分なのだが…
■著者:マリオ・バルガス=リョサ著, 田村さと子訳
■書誌事項:河出書房新社 2008.1.10 516p ISBN4-309-70942-7/ISBN978-4-309-70942-0
■原題:El Paraíso en la Otra Esquina: Mario Vargas Llyosa, 2003



