A Widow for One Year, 1998
 |  |
| 都甲幸治,中川千帆訳 新潮社 2000.6.30 2,300円 |
| 上:ISBN4-10-519108-X下 | 下:ISBN4-10-519109-8 |
(ジョン・アーヴィング・コレクション)
都築まゆ美〔装画〕,新潮社装幀室〔装丁〕 |
1958年、ロングアイランド。4歳の少女ルースは、母がアルバイトの少年エディとベッドにいるところを目撃する。死んだ兄たちの写真におおわれた家。絵本作家で女ったらしの父。悲しみに凍りついたままの母は、息子たちの写真だけもって姿を消う。母を失ったルースと、恋を失ったエディがのこされた。夏が終わろうとしていた―。母の情事を目撃してから37年。こわれた家族とひとつの純愛の行きつく先は?/1990年、ニューヨーク。いまや世界的人気作家のルースは、冴えない小説家のエディと再会する。アムステルダムで彼女は、父の絵本のモグラ男そっくりの犯人が、娼婦を殺害するのを見てしまう。5年後。ルースは幼子を抱えた未亡人。エディは相も変わらぬ独身暮らし。謎のカナダ人作家の存在が二人をゆすぶり、オランダ人の警官まであらわれて...。遠い夏の日から37年。毀れた家族と一つの純愛の行きつく先は?圧倒的ストーリー展開、忘られぬ人物造形、緻密なディテール、胸を打つエピソード、そして登場人物の手になる小説内小説―。長篇小説の愉しみのすべてがここにある。
「サイダーハウス・ルール」で一つの頂点を迎え、落ちることなくまた面白くなってきた。「サイダーハウス・ルール」以前は、なんのかんの言っても同じモチーフを近いテーマを繰り返し扱っていたのが、それ以後は様々な舞台、様々なテーマに広がって行き、そして、1990年代最後の作品で、本当に上手い「枠」のある物語をつくったものだと。
マリアンにはじまり、マリアンに終わる、素晴らしいエンディングである。エディとルースが再び出会って恋にでもおちたら、それはそれでいいのだけど、ありきたりだなぁと思いながら読み進めて行くと、なかなかじらされる。
それでも「愛と暴力」は変わらない。家族の物語であり、ラブストーリーであり、作家論であり、ミステリでもある。一つ一つの要素に上手下手はなく、すべてがうまく織り込まれている。アムステルダムで殺人事件を目撃するルースが殺されはしないかと、本当にドキドキした。
タイトルは未亡人の姿を描いて読者に「これは本物の未亡人ではない」と読者に罵倒されたルースが、自分が未亡人になってみると、かつて自分が書いた未亡人の姿にそっくりなことに驚く、という部分から出ているのだろう。物語の力を信じて小説を書くが、逆説的に「個人的体験を物語にすること」を余儀なくされていくルースの姿を描いている。「物語」と「個人的体験」との差を感じさせずにはいられない文学ジャーナリズムへの皮肉なんだろうなと想像する。アーヴィングを読んでいると、本来はそれを区別することに意味はなく、両方をどう昇華させていくか、で物語が決まるのではないかという気がする。
それにつけても子供を失った親の哀しみの深さというものは、とてつもなく大きいのだとマリアンを見ていると思う。自分の子供でさえその哀しみに巻き込まないようにする、子供を失う哀しみをもう一度味わいたくないから子供を捨てるマリアンの心情。
人から見たら「変人」と言わざるを得ないほどのエディの「ピュアな愛」とアメリカ的とも言える、ハナやテッドの「消費する愛」の対比も見事だ。
他のものもいろいろ混ぜながら、ぼちぼちとだが、結局「熊を放つ」から10作品を半年近くかけて読み終えることができた。はじめて読んだのは「オウエンのために祈りを」からだが、じっくり読み直すことができた。充実感は満点。やってみてよかった。
 |  | 2005.8 新潮文庫
上:ISBN4978-4-10-227308-1
下:ISBN978-4-10-227309-8
都築まゆ美〔装画〕,新潮社装幀室〔装丁〕。映画公開にともない表紙はワンシーンを使ったものになったが、意図的にこの装画を使った。 |
 ■著者:野沢尚
■著者:野沢尚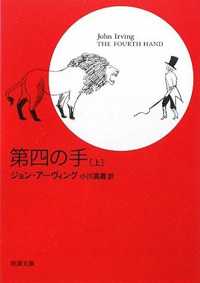

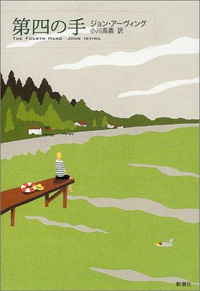







 ■Farway so close! 147min 独 1994.5
■Farway so close! 147min 独 1994.5


