かなしい生きもの
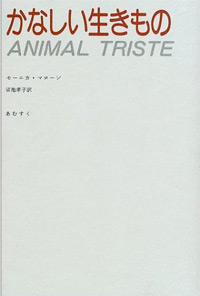 モーニカ・マローンは1941年生まれの東独ベルリン出身の作家。1981年に西側でデビューした。この作品は50代になってから書かれたもので、ちょうど語り手が舞台としている時代の歳頃と同じ位だろうと思う。最初は語り手の女性が何歳なのか、何年頃なのかの設定もわからず、次第に明らかにされていくが、時折また記憶があやふやになっていく。「実際の起きたことと起こり得たことの違い」という表現がされているが、彼女の妄想なのか、実際に起きた事実なのかをあやふやにしながら、時に真実を明確に語りながら、物語は進んでいく。
モーニカ・マローンは1941年生まれの東独ベルリン出身の作家。1981年に西側でデビューした。この作品は50代になってから書かれたもので、ちょうど語り手が舞台としている時代の歳頃と同じ位だろうと思う。最初は語り手の女性が何歳なのか、何年頃なのかの設定もわからず、次第に明らかにされていくが、時折また記憶があやふやになっていく。「実際の起きたことと起こり得たことの違い」という表現がされているが、彼女の妄想なのか、実際に起きた事実なのかをあやふやにしながら、時に真実を明確に語りながら、物語は進んでいく。
ちょうど1989年のベルリンの壁の崩壊以後にベルリンの街がダイナミックに変化し、人々の価値観も変化しつつある時代に生きた女性の物語として読むと興味深い。戦争帰りであるその親の世代との世代間ギャップ、彼女の世代における夫婦間のギャップ、娘世代との世代間ギャップ等、激しく変わる時代の中で生きた彼女が信じられるものがなかったのは確かだろう。彼女が唯一信じていた「ブラキオザウルスの前での出会い」のことを気軽に不倫相手の妻に話されて彼女は壊れてしまう。「戻ってくる」という言葉を信じなかった結果が結末だ。
物語の間ずっと不倫相手だった「フランツはもう戻ってこない」と彼女は語り続ける。読者に「何故戻ってこないのか?彼はどこに行ったのか?」という興味で引っ張りながら、上記の時代を生きた女性の不信感というものを突きつける構造になっているのだが、全体として言うと、読み進めるには私にとっては少々厳しいものがあった。確かに、途中に入る過去のエピソードは面白い。特に犬の誘拐の件、「カーリンとクラウス」の件など。しかし、全体的に引っ張れないため、これだけの長さの小説にしては途中なんども放り出しそうになった。多分、50代の不倫っていうのが、あまりに興味が持てないジャンルだからだろうと思う。
できれば、この作者のもう少し前のものを読みたい。が、翻訳されているのは、現在のところこれだけだ。
■著者:モーニカ・マローン著,梁池孝子訳
■書誌事項:あむすく 2001.12.4 195p ISBN978-4-900621-22-0/ISBN4-900621-22-6
■原題:Animal Triste, Monika Maron, 1996
=====
memo
Flight of Ashes (Flugasche), 1981<飛散する灰>
Herr Aurich, 1982
Das Mißverständnis, 1982<誤解>
The Defector (Die Überläuferin), 1986<寝返った女>
Silent Close No. 6 (Stille Zeile Sechs), 1991
Nach Massgabe meiner Begreifungskraft: Essays und Artikel, 1993
Animal Triste, 1996<かなしい生き物>
Pavel's Letters (Pawels Briefe), 1999
Endmoränan, 2002
quer über die Gleise, 2002
Wie ich ein Buch nicht schreiben kann und es trotzdem versuche, 2005




