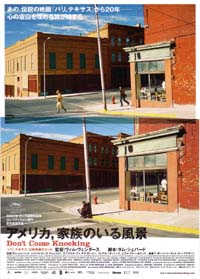破滅者―グレン・グールドを見つめて
 ■原題:Der Untergeher : Thomas Bernhard, 1983
■原題:Der Untergeher : Thomas Bernhard, 1983
■著者:トーマス・ベルンハルト著,岩下真好訳
■書誌事項:音楽之友社 1992.7.25 ISBN4-276-21412-2
■感想
グレン・グールドについて書かれた伝記ではまったくない。事実にも基づいてないし、主人公ですらない。騙された人は多いんじゃないだろうか。でも、クラシック音楽ファンが読まないと実は楽しめないという不思議な小説である。
内容的にはグレン・グールドという実在のピアニストについて書かれているのではなく、グレン・グールドとザルツブルクで一緒にホロビッツの門下で学んだ(史実にはない)というやはりピアニストであるヴェルトハイマー、そして語り手である「私」の3人の男の50年を描いた物語である。というとわかりやすいのだが、実はまったく「物語」などといえるような代物ではなく、「私」が3人に関しての思考を、少しずつ少しずつ階層を変え、変奏しながら進行するという不思議な語り口になっている。訳文は読みやすくするために適当に改行が入っているが、原文はどうやらセンテンスまったくなしという状態らしい(ケルアックみたい)。
一番主な人物はヴェルトハイマーで、彼が自殺したと聞いて、友人である「私」が葬式に行き、その帰りに彼が最後に住んでいたトライヒという町の旅館に宿泊しようとチェックインするところで小説は開始される。そして、3人が出会ったところから始まり、直前の葬儀の様子までを時系列を無視してぐるぐるとまわりながら、チェックインするところで、一息入れる。が、そのときはすでに話は終盤なんである。そしてチェックインして女将と話し、彼の最後に住んでいた家に行って、終わる。なんだか、3人の男たち一代記のようで、まったくそうではないというのが、読後「何と説明してよいものやら」という戸惑いを隠せない。
Untergeherという原題は直訳すると「下へ行く人」=落ちぶれた人、堕落者、で、この場合は破滅者と訳している。この破滅者はグレン・グールドではなく、ヴェルトハイマーのことを指す。ヴェルトハイマーがグレン・グールドに出会い、そのピアノ(ゴルトベルク協奏曲)を聞いた瞬間に、彼は破滅する運命にあったという主題が、何度も何度も繰り返される。その間に「私」がいかにピアノを捨てることが出来たか、ピアノを捨てることで生き延びたかという話も何度も何度も繰り返される。さらに、ヴェルトハイマーが捨てきれず、未練たらたらで、そのせいで自殺するしかなかったかのような、それでいて本当の原因は彼の元を去った妹のせいであるかのような、矛盾している話がずっと繰り返される。
繰り返すのは単純に繰り返しているのではなく、少しずつ位相を変えていくというか、違うバリエーションになっていくところが不思議な感じだ。一見だらだらしているようだが、リズムに載って読み進めることが出来る。どうやら、小説自体が変奏曲になっているようだ。その辺はある程度クラシック音楽の知識があった方が楽しめる作りになっているらしいのだ。
とはいえ、音楽之友社からオースラリアの作家の作品が出版されていたとは、気付かない。独文の現代作家は1990年代の日本ではまったく恵まれていなかったことがよくわかる。文芸出版社からは出せなくて、なんとか音楽関係者の目を惹こうという目論見で刊行されたのだろう。苦労が忍ばれる。最近また注目度があがったからよかったようなものの、誤解されっぱなしになってしまったところだ。
当分ベルンハルトで行こう。唐突に放り投げるかもしれないが。