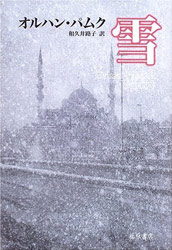ミネハハ
 ヴェデキントの本が出ていると気づいたとき、とても驚いた。理由を探すとこの作品を原作とする映画「エコール」が公開されたためだという。なるほど。しかし、なぜ市川実和子?妹の実日子は好きだけど‥と思って後書きを読むと、「戸田史子さんが、原文のドイツ語からまっすぐに訳してくださったものを、 わたしが自分の言葉に色染めていく。」とある。一応「ドイツ語会話」に出ていたこともあってドイツ語は多少はわかるらしいが、これで翻訳と言えるのか‥?彼女の文章にはある意味なっているのだろうけど、不可解だ。リトルモアが出した理由もよくわからない。
ヴェデキントの本が出ていると気づいたとき、とても驚いた。理由を探すとこの作品を原作とする映画「エコール」が公開されたためだという。なるほど。しかし、なぜ市川実和子?妹の実日子は好きだけど‥と思って後書きを読むと、「戸田史子さんが、原文のドイツ語からまっすぐに訳してくださったものを、 わたしが自分の言葉に色染めていく。」とある。一応「ドイツ語会話」に出ていたこともあってドイツ語は多少はわかるらしいが、これで翻訳と言えるのか‥?彼女の文章にはある意味なっているのだろうけど、不可解だ。リトルモアが出した理由もよくわからない。
フランク・ヴェデキントは私には思い入れの深い作家だ。なんといっても卒論が「地霊・パンドラの箱」なのだから。しかし「ミネハハ」という作品のことは知らなかった。というのも、劇作家だと思っていたからではないかと思うが、なにぶん当時はほかに翻訳されていたのが「春のめざめ」だけなのだから、仕方ない。
ところで、映画「エコール」はストレートに「ロリータ」好きにはたまらんというものらしい。そういう内容だから当然だろう。しかし、女性監督なので、おそらくは本来は少女の美しい姿が描きたかっただけなんだろうと推察できる。ともあれ、見ていないのだから何とも言えない。見たい気もしないではないが、今一つ乗り気になれない。
ヴェデキントは当時とんでもなく危険な劇作家だったのだろう。実際検閲にあい、発禁処分になっている。今読むと、むろんそんな危険な感じはせず、美しい物語になってしまっている。おそらくは孤児院か何かで育てられた女の子が7歳くらいで箱に入れられて運ばれてきて、その後初潮を迎えるまでの間、外界から隔絶された森の中の学校で教育を受ける。女の子たちは年齢の違う子でグループを形成し、上級生は下級生の面倒をみるというシステム。彼女たちの身の回りの面倒を見る老婆がそれぞれのグループに二人いて、逃げだそうとして、と一生ここから出られずに女の子たちの面倒をみさせられると教えられ、誰も逃げだそうとはしない(映画では逃げだそうとする子が死んでしまう)。ある一定の年齢になると夜は少し離れた劇場で踊るようになる。それが学校の収入源らしい。どんな客が来ていて、そんな人物が経営しているのかなどはまったく語られていない。一瞬、いわゆる洗脳の物語かと思ってしまったりもしたが、外に出てから普通の生活をして来た人が語り手になっているので、それもなさそうだしな‥と思っていると、学校の正体はよくわからないまま終わってしまう。
何にせよヴェデキントの作品を日本語で気軽に読めたのだから文句はないが、どうもおかしな取り上げられ方だなと思わざるを得ない。
■著者:フランク・ヴェデキント著, 市川実和子訳
■書誌事項:リトルモア 2006年10月19日 118p ISBN-89815-186-8
■原題:Frank Wedekind : MINE-HAHA, 1903