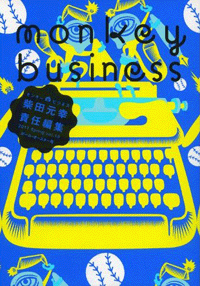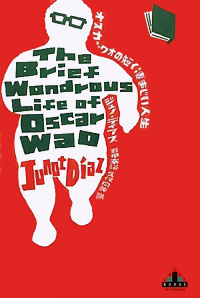カンポ・サント/W.G.ゼーバルト
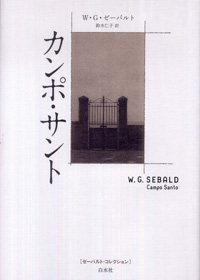 白水社のゼーバルト・コレクション5冊目。まとまった一つの作品ではなく、三部集のような体裁だ。
白水社のゼーバルト・コレクション5冊目。まとまった一つの作品ではなく、三部集のような体裁だ。
散文4本はコルシカ島探訪の紀行文。うまく続かずに頓挫してしまったものらしい。しかし、ちょっと紀行文なんだか現実なんだか幻想なんだかよくわからないところが、ゼーバルトらしい。この声高に叫ばない静かな筆致が何より好きだ。一方でトーマス・ベルンハルトのような罵倒しまくりも好きなところが、我ながらよくわからない。
私は亡霊や幽霊が普通に出てくる話が比較的好きだ。と言ってもオカルト好きなわけではない。日本人にとってはそんなに遠い存在ではないように思える。悪いのもいるが、みんながみんなそうではない。なんというか、自然にいるものとして認識している。ゼーバルトのお話に出てくる幽霊もそんな感じ。人間にとっては当たり前の存在のように登場している。ここにあるコルシカ島での死者の扱いに親近感を覚える。
エッセイの方になると、書かれた時期が違うこともあり、急に堅苦しい論文になる。それも時代を経て徐々に穏やかになっていくのだが。主にドイツ文学に関するエッセイ群である。
最初はペーター・ハントケの「カスパー」だが、ハントケの作品に限らず、カスパー・ハウザーについては独文者なら、うんざりするほど接しているだろう。文学や映画の素材として取り上げられることも多く、ゼーバルトもドイツ人・同時代人としてペーター・ハントケの戯曲に触発されるものがあったのだろう。
「歴史と博物誌のあいだ」は「空襲と文学」に内容は近い。第二次世界大戦で壊滅されたドイツの空襲を取り上げた数少ない作品、カザック、ノサック、クルーゲをとりあげている。「哀悼の構築」も引き続き戦後文学についてのエッセイ。ギュンター・グラス「蝸牛の日記」とヴォルフガング・ヒルデスハイマー「テュンセット」を中心に、第二次大戦直後、犠牲者を哀悼する文学が欠落していることを取り上げており、「空襲と文学」のテーマに寄り添っている。
二本のエッセイでカフカに触れている。1本目の「スイス経由、女郎屋へ」はカフカがマックス・ブロートとともにプラハからスイス、イタリア、パリを旅した日記に寄せたエッセイ。もう1本の「カフカの映画館」では冒頭、ヴィム・ヴェンダース監督の「さすらい」が取り上げられている。あまりの意外さに驚きながら読み進めていくと、主演のうちの一人、ハンス・ツィッシュラーの著書についてのエッセイだった。ハンス・ツィッシュラーは俳優としてのみならず、翻訳家、映画監督、演劇プロデューサー、出版人などマルチな人で有名だ。これまであまり触れられることのなかった内容のカフカ研究書「カフカ、映画に行く」を書いていた。これは知らなかった。
「赤茶色の毛皮のなぞ」はチャトウィンの「どうして僕はこんなところに」を読もうと思っていたところなので、タイミングが非常によかった。私は「パタゴニア」しか読んだことがないのだが、これがとても好きな本で、紀行ものとしては自分の中では3本の指に入る。ここにあるニコラス・シェイクスピアの「ブルース・チャトウィン」という伝記、誰か訳してくれないものか。
こういう評論集を読むと、W.G.ゼーバルトはやはり同時代の人だったんだなとつくづく感じる。池澤夏樹の解説が最後についているのだが、ほぼ同年代だそうだ。本当にこれから、というときに亡くなったんだなと思う。もったいない。このシリーズも残るは「アウステルリッツ」の改訳のみ。なぜ改訳を出すのかは出てみてからわかるだろう。新作はもう読めないのだなと思うと残念でしかたがない。
■書誌事項
W.G.ゼーバルト著,鈴木仁子訳
白水社 2011.3.30 216p ISBN978-4-560-02733-2
■目次
散文
アジャクシオ短訪
聖苑(カンポ・サント)
海上のアルプス
かつての学舎の庭
エッセイ
異質・統合・危機―ペーター・ハントケの戯曲『カスパー』
歴史と博物誌のあいだ―壊滅の文学的描写について
哀悼の構築―ギュンター・グラスとヴォルフガング・ヒルデスハイマー
小兎の子、ちい兎―詩人エルンスト・ヘルベックのトーテム動物
スイス経由、女郎屋へ―カフカの旅日記によせて
夢のテクスチュア
映画館の中のカフカ
Scomber scombrus または大西洋鯖―ヤン・ペーター・トリップの絵画によせて
赤茶色の毛皮のなぞ―ブルース・チャトウィンへの接近
楽興の時
復元のこころみ
ドイツ・アカデミー入会の辞