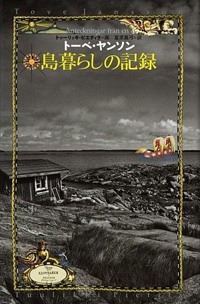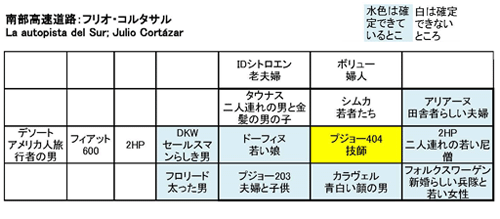河出書房の世界文学全集、南米で初訳だけという限定で買おうとしたら結局「楽園への道」だけになってしまった。初訳はないが「南部高速道路」をトップに持って来たというセンスの良さと、ルルフォを欠かさなかった正しさを評価して、「短篇コレクションI」を読んでみた。
河出書房の世界文学全集、南米で初訳だけという限定で買おうとしたら結局「楽園への道」だけになってしまった。初訳はないが「南部高速道路」をトップに持って来たというセンスの良さと、ルルフォを欠かさなかった正しさを評価して、「短篇コレクションI」を読んでみた。
フリオ・コルタサル「南部高速道路」
この作品、「悪魔の涎・追い求める男」ではなく、『ユリイカ』1983年7月号の「ラテンアメリカ文学」で初めて読んだ。そのとき作りたいと思っていたものを、今回良い機会なので、作ってみた。
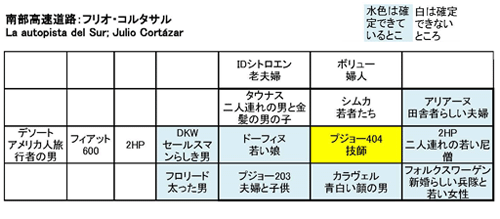
クルマの配置図なのである。1列12台だが、外側は省略した。プジョー404を中心にしているが、前のシムカとタウナスの位置関係がわからない。読むと、両方ともプジョー404の前のように見える。また今ひとつ確認できないのが、IDシトロエンとボリューだ。誰か、これが正しいというのを教えて欲しい。
この話はいわば都会の遭難物語なのである。8月からたぶん11月か12月頃にかけてのパリに向かう道路が舞台。片側6車線の上下線を合わせ12車線全部を上りにしているから上記の図は右にあと3台、左にあと2台いるはず。食料や水の確保、医療や看護の相互扶助等からリーダーが自然発生的に生まれ、共同体が創設される。その中では諍いも起こるし、他のグループとの駆け引きも発生するし、中には失踪する者あり、自殺する者あり、病死する者あり、妊娠する者ありという、不条理というか(来るはずのものを待っているからゴドー待ち?)ファンタジイというか、少し変わった物語が進行する。最後に渋滞が突然解消され、共同体は崩壊する。日常の中での遭難というテーマがおもしろくて、この話はよく覚えている。
オクタビオ・パス「波との生活」
この作品には「波と暮らして」という訳もある。どちらの方が正しいかなんて、私にはわからない。この先二人でどうやって逃げるのだろう、わくわく、と思わせて、一瞬で捕まって1年経ってしまうという展開は時間の使い方が意表をつく。
フアン・ルルフォ「タルパ」も昔のメキシコの聖人信仰の強さなど知らないとわからないかもしれない。それにしても暗い...底抜けに暗いけど、ルルフォ短篇の完成度の高さ、流れの美しさには毎回感動を覚える。
張愛玲「色、戒」
戦前から戦時中初期の中国のスパイものって、こういう雰囲気にならざるを得ないのか。衣装とかきらびやかさは「上海バンスキング」?二人で「相手は自分を愛している」と思っているところがおもしろい。
ユースフ・イドリース「肉の家」
イスラームの禁欲主義から、こんなえぐい話が出来てしまう。日本も戦前の田舎で、封鎖的で人の目がうるさそうなところほど、夜這い文化があったりするからなぁ。でもこの話、目の見えない人をなめてるでしょう。こんなの、絶対わかると思うよ。
P.K.ディック「小さな黒い箱」
黒い箱ってiPhoneの黒ですか?なわけない。テレビの前においた取っ手のついた黒い箱で宇宙人と交流できるSF。禅ブームだったアメリカの頃を思えば古くさいと感じられるし、この黒い箱をガジェットの一つと思えば新鮮に感じられる。
チヌア・アチェベ「呪い卵」
短いながら、天然痘のせいで人気のなくなった市場の恐ろしい空気がじわっと感じられる作品。キーワード一つ一つが私の思うアフリカ文学らしさ満載だ。「キティクパ=天然痘」「お飾りをもらう=天然痘にかかる」「夜の仮面」「鈍いの卵」等。ナイジェリアというと、どうしても知人のアフリカ人のビジネスマンを思い浮かべてしまうのだが、大きく外れてはいないのかもしれない。
金達寿「朴達の裁判」
なるほど、プロレタリア文学にユーモアは少ない。みんなきまじめすぎる。こんな転向してばかりの主人公は通常の左翼文学では許されないだろう。それにしても、100ページ近い。これは短篇か?。
ジョン・バース「夜の海の旅」
「泳ぐ」を「生きる」と読み替えて読むと、すんなり読めてしまう。
ドナルド・バーセルミ「ジョーカー最大の勝利」
アメコミが嫌いなので、全然わかりません。
トニ・モリスン「レシタティフ─叙唱」
白人と黒人の女の子が8歳のときに児童養護施設で知り合って、その後大人になって再会し...なんていう出だしだったので、ベタベタな友情ものを一瞬想像したが、そんなことはまるでなかった。意図的にどちらが黒人でどちらが白人かわからないように描かれていて、あえて混乱させようと、人種的アイデンティティをわからなくさせてから読ませようとしている。私は「ロバータは黒人、トワイラは白人」と根拠なく決めて読んでいた。そうでもしないと居心地悪くて読み進められなかったからだ。この紀要の「人種をこえる娘たち」が詳しい。
リチャード・ブローティガン「サン・フランシスコYMCA讃歌」
よくわかりませんが、おもしろいかな。
ガッサーン・カナファーニー「ラムレの証言」
人にやられてイヤだったことは人にするのをやめましょう...という民族的記憶というのは存在し得ないのだろうか。老人と少年の視線が交錯したそのとき、引き継がれた何かがあったのだということが、じわっとわかる。哀しい記憶が引き継がれてしまったのだろう。
アリステア・マクラウド「冬の犬」
雪と氷に閉ざされた冬の厳しさとゴールデンリトリバーの黄金色の毛のふさふさ感がなんともいえずマッチしていて、カナダらしいと言えばそうなのだが、何とも感じの良い作品だ。カナダっていうとこういうイメージだが、日本の東北っぽさがないのは、海のせいか、木の高さのせいか?
レイモンド・カーヴァー「ささやかだけど、役にたつこと」
パン屋がなぜ「こんなふう」になってしまったのか。空虚な人生を送って行くことが、どれほどの対価を支払わなくてはならないことになるのか、というお話かなと。彼は少しでも取り戻すように、若い夫婦と夜を徹して話しているのだろう。
マーガレット・アトウッド「ダンシング・ガールズ」
「緑したたる未来の楽園はあらかじめ失われている」それでも夢を見てもいいでしょう?アラブの民族衣装を着た彼ら、みんなが一緒にいるところを。いい話だと思う。さすが岸本佐和子訳。ジャンル的に積極的には読まないが、文芸誌やアンソロジーで見かける岸本さんの訳された作品はおおむねおもしろい。
変な下宿屋で息が詰まるお話かと思いきや、なかなか愉快。それにしてもどうして狭量な中年女性の子供は、頭の悪い粗野な子供になるんだろうな。
高行健「母」
懺悔の話なのだけれど、「僕」というのが辛くなって、「彼」と言ってしまって混在しているところが、すごくいい。中国人は親を、子を大切にするものだと思っていたのだけど、文革とか天安門とか、いろいろあったからかな。こういう物語が出てくるのは。
ガーダ・アル=サンマーン「猫の首を刎ねる」
比較的最近見たテレビでイスラム圏から日本に留学している若い女性が「自分の国では貧乏な男とぶさいくな女は一生結婚できない。」と言い切っていた。一夫多妻制だから財産のある男のところに美人が集中し、子供もそこでたくさん産まれるから、それでいいらしい。と語る留学生本人は美人だったけど、それがイヤで留学してるんだろうに。テレビで顔を出すなんて、ナディーンのバンジージャンプ並にすごいことでは?それにしてもおばさんの花嫁の口上はすごい。奴隷どころか、二次元の女の子以上ですよ、みなさん。
目取真俊「面影と連れて」
沖縄の話というと、戦前戦時中の話が多いのだが、これは戦後(1955)~海洋博(1975)の頃の話。うっすらと記憶に残っている。主人公の女性は逆子で産まれてきて、少し知的な遅れがあって、親からは見捨てられ、小学校でいじめにあって登校拒否になる。悲惨と言えばそうなのだけど、不思議とそんな感じはしない。
■書誌事項:河出書房新社 2010.7.1 ISBN978-4-309-70969-7
■内容:
「南部高速道路」フリオ・コルタサル著,木村榮一訳 Julio Cortázar : La autopista del sur, 1966 (「悪魔の涎・追い求める男」1992)アルゼンチン
「波との生活」オクタビオ・パス著,野谷文昭訳 Octavio Paz : Mi vida con la ola (「鷲か太陽か?」2002)メキシコ
「白痴が先」バーナード・マラマッド著,柴田元幸訳(「喋る馬」2009)アメリカ合衆国
「タルパ」フアン・ルルフォ著,杉山晃訳 Juan Rulfo : Talpa, 1950 (「燃える平原」1990)
「色、戒」張愛玲著,垂水千恵訳(新訳)上海
「肉の家」ユースフ・イドリース著,奴田原睦明訳(「集英社ギャラリー 世界の文学 20 中国・アジア・アフリカ」1991)エジプト
「小さな黒い箱」P.K.ディック著,浅倉久志訳(「ゴールデン・マン」1992)アメリカ合衆国
「呪い卵」チヌア・アチェベ著,管敬次郎訳(新訳)ナイジェリア
「朴達の裁判」金達寿著(「金達寿小説全集6」1980)在日朝鮮
「夜の海の旅」ジョン・バース著,志村正雄訳(「アメリカ幻想小説傑作集」1985)アメリカ合衆国
「ジョーカー最大の勝利」ドナルド・バーセルミ著,志村正雄訳(「帰れ、カリガリ博士」1980)アメリカ合衆国
「レシタティフ─叙唱」トニ・モリスン著,篠森ゆりこ訳(初訳)アメリカ合衆国
「サン・フランシスコYMCA讃歌」リチャード・ブローティガン著,藤本和子訳(「芝生の復讐」1976)アメリカ合衆国
「ラムレの証言」ガッサーン・カナファーニー著,岡真理訳(『前夜 2005年春号』2005)パレスチナ
「冬の犬」アリステア・マクラウド著,中野恵津子訳(「冬の犬」2004)カナダ
「ささやかだけど、役にたつこと」レイモンド・カーヴァー著,村上春樹訳(「大聖堂」2007)アメリカ合衆国
「ダンシング・ガールズ」マーガレット・アトウッド著,岸本佐和子訳(「ダンシング・ガールズ」1989)カナダ
「母」高行健著,飯塚容訳(「母」2005)中国
「猫の首を刎ねる」ガーダ・アル=サンマーン著,岡真理訳(初訳)シリア
「面影と連れて」目取真俊著(「魂込め」1999)沖縄
 外国文学の読者の間であまりにも評判が良いので、ついに耐えきれず、読んでしまった。岸本佐和子さんの訳だし、ミランダ・ジュライは映画の評判もいいし、何より本人がとてもキュートだし、おもしろくないはずはない。それでも現代のアメリカ人女性(特に白人)の書く短編小説が好きになったためしがないから躊躇していたのだ。どうしても「共感」を要求してくる部分があって、それが受け付けないのだろうと思う。私はもともと小説に中途半端な共感を求めていないのだ。まるで知らない世界の人たちが何を考えているのかが知りたいのだから、遠ければ遠いほど興味がもてる。
外国文学の読者の間であまりにも評判が良いので、ついに耐えきれず、読んでしまった。岸本佐和子さんの訳だし、ミランダ・ジュライは映画の評判もいいし、何より本人がとてもキュートだし、おもしろくないはずはない。それでも現代のアメリカ人女性(特に白人)の書く短編小説が好きになったためしがないから躊躇していたのだ。どうしても「共感」を要求してくる部分があって、それが受け付けないのだろうと思う。私はもともと小説に中途半端な共感を求めていないのだ。まるで知らない世界の人たちが何を考えているのかが知りたいのだから、遠ければ遠いほど興味がもてる。